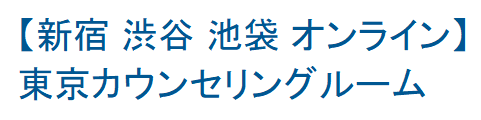心理学の扉を叩くと、ほどなく「認知」という言葉に出会います。
認知という機能は、眼前に広がる無機質な事実に彩りを与え、意味を吹き込み、一つの「物語」へと編み上げる営みといえます。
一匹の猫を目の当たりにしたとき、それを愛らしいと感じて微笑む人もいれば、恐怖を覚えて身を引く人もいます。どちらも、その人の内側で機能している認知の働きによるものです。そこには育まれてきた過去の記憶と、未来への予感とが複雑に織り込まれています。私たちは、認知というフィルターを通してのみ、この世界を理解し、生きていくことができます。
「認知」という概念を臨床心理学の歴史の中で辿ると、アーロン・ベックの存在を避けることはできません。ベックはフィラデルフィアを拠点に、近代的な心理療法の一つである認知行動療法の理論的基礎を築きました。著書『Cognitive Therapy and the Emotional Disorders』(1976年)において、彼は「認知の歪み」を「現実を不正確、あるいは非合理に解釈する思考のパターン」と定義しました。抑うつや不安の背景には、事実を歪めて捉える「機能不全な認知プロセス」がある。これが、彼の基本的な立場でした。
しかし、ここで一つの根源的な問いが浮かび上がります。猫を「かわいい」と認知することは「正確」なのでしょうか。猫を「怖い」と認知することは「非合理的」なのでしょうか。
突き詰めて考えるならば、あらゆる認知には、本来、正解、不正解は存在しません。「認知」に正解を定めるという前提そのものが、個人の内的な真実を抑圧する一つの偏りになりかねません。そこに認知があるとき、ただその認知が存在しているだけなのです。
会社の上司から”パワハラをされた”、夫から”愛されている”、コミュニケーションが”苦手”、どの認知も、正しいわけでも、間違っているわけでもない。厳密に言えば、すべての認知は自分がそう色づけた、というだけ。そうした色付けの連続が、その人の生きる中で紡いでいく固有の物語となっていくのです。私たちは事実そのものではなく、自分自身が認知を重ねて作り上げた浅き夢を人生として楽しんだり、あるいは苦しんだりするのです。
カウンセリングとは、ある「認知」を「誤り」と断じ、「正しい」認知へと一方的に修正する作業ではありません。その人自身の物語の中で辻褄が合わなくなってしまった認知について、あるいは社会の多数派とは異なる認知について、言葉を交わし、理解していく取り組みです。
来談者は、自分が作り上げた物語が破綻しかけていたり、もしくは多くの人が描く共通の物語から、ほんの少しだけ距離がある状態になってしまっているのです。
そういった認知が、本人にとって耐えがたい「生きづらさ」となっているのなら、そこには新しい物語を紡ぐための契機が佇んでいます。認知を変えるという行為は、単なる思考の修正ではありません。それは、親や恋人、あるいはこれまでの自分自身との関係性の中に流れていた旋律を書き換え、人生の物語そのものを再編成していく、極めて繊細で、尊厳を伴う作業です。悲しみに別の意味を与え、痛みを抱えながらも前を向けるような新しい章を書き足していくこと。その「物語の再構築」を静かに見守り、共に歩むこと。それこそが、心の平穏を取り戻すための一つの道筋であり、世界を編み直す、カウンセリングという取り組みなのです。